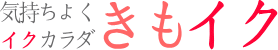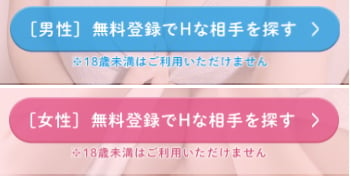女性用風俗の極上の悦びに堕ちていく人妻|夫の浮気とイケないオナニーが後押しする快楽

出張ホスト、レンタル彼氏、性感マッサージ店。
明確な名称やジャンル、サービスは違えど、1つに括ってしまえば、全て女性用性風俗だ。
そんな店を利用するのは、寂しくて欲求不満な女だけ。
寂しいのは同じだけど、私は利き手と玩具で満たされてるから欲求不満じゃない。
そんなの必要ない、必要ない…
日々、私は自分にそう言い聞かせていた。
“心身共に満たされない貴女に極上の悦びをお約束します”
しかし、そんな胡散臭い甘言が、頭から離れないのも事実だった。
蜜な夜の始まり
常夜灯に照らされた寝室。
専業主婦である春岡小麻知は、夫の彬が出張で家を空けている夜、マスタベーションに耽っていた。
「んっ、はぁっ、…ぁっ、」
確かな熱と湿りを孕む、彼女の嬌声が響いては、煙のように空気に溶け込んでいく。
圧し殺し切れない細い声や吐息が、馴染み深くも変哲のない寝室ごと淫靡な空間へと変え、小麻知の中に沸き出す”女の欲望”を刺激した。
“悔しかったら、小麻知も浮気の1つくらいしてみろ。まあ、そんな勇気がないお前には到底無理だろうがな”
ある日、彼女が勇気を振り絞って、彬に浮気してるのか問い詰めたら、認める答えと共にそんな煽り言葉を口にした。
結婚10年目、愛し合ったのは両手に収まるだけ。
ここ数年では、お互い口数も少なくなり、業務的な最低限の会話しか交わさなくなっていた。
そんな冷え切った夫婦生活での、彬の浮気発覚後だった、独りの淫行に小麻知が耽るようになったのは。
惰性的に行い始めた時は、指を入れてクリトリスを触るだけで満悦だった。
しかし、刺激に慣れてきたのか、数を重ねる程に、自身の手では満足できなくなっていた。
最近では、太めの硬い男性器を模したバイブも併用して、やっと悦びを得ている。
ベッドの上で、脚をM字に開脚したまま、小麻知は湯上がりの火照りが残る、局部の秘豆へ指を伸ばした。
「はぁっ…んぁっ、」
薄い皮を纏うそれを、薬指の腹で軽く押し潰すように触れば、恍惚とした熱が全身を巡り、筋肉の自由をゆっくりと奪っていく。
それと同時に、脳内に残る鬱々とした雑念も溶かしていき、ちょっとした解放感に包まれた。
鈍い痺れや疼きで、思わず閉じそうになる太股をピクピク振るわせながらも、小麻知は指の腹と爪先で与え続けた。
好みのリズム、速さを乱さないよう、腹や爪先に、痛みを生まない力加減を保ち続けるのも忘れない。
微弱ながらも、律動的な振動を受け続けた突起物は、鮮やかに血色と硬さを持ち、皮を破って頭を出していた。
そんな変化を指先で感じ取ると、小麻知は下半身から手を離し、そのまま口許へ運んだ。
そして、唇から唾液を存分に染み込ませた舌を限界まで伸ばし、女精の香りが仄かに残る指先を、ゆっくりと舐め上げた。
充分に湿りを持たせると、再び秘部へ手を伸ばし、図々しく自己主張する硬い豆にも潤いを与えた。
独りの悦楽
「はぁっ…あぁんっ…!」
乾燥した指先で得た時はまた違う恍惚とした感覚に、小麻知は部屋中に響く程の甲高い声を上げ、上半身を弓なりに反らして天井を仰いだ。
体液の程好い粘度と湿りが生み出した新たな官能は、深く、そして濃蜜で、彼女を貪欲にさせた。
サウナに入っているような湿った熱に侵されながらも、小麻知は徐にもう片方の手も同じ場所へと伸ばし、ぷっくりと赤く膨れた秘芯の下の、厚みのある肉襞をそっと掻き分ける。
そして、その先の、ヒクヒクと不規則な収縮を見せる秘口へ、2本の指先を埋め込んだ。
するとそこは、侵入や暴露を望んでいたかのように、細い異物へ執拗に絡んできた。
強い密着を受けながらも、小麻知は静止させた指の腹を、入り口付近の内壁へ擦り付けた。
外からの刺激を受け続けた内側の肉は、しっとりと潤いを纏っていて、動きに円滑さを与えた。
「はっ…ぁっ、ぁっ…ぁぁっ、」
間隔の短い嬌声を溢すと共に、小麻知は不規則な発声と呼吸を繰り返した。
瞼を硬く閉じ、眉間には薄い皺を刻み、表情を歪めているが、彼女は苦しさを感じてはいなかった。
だが、熱に浮かされた頭でも、彼女は自覚していた。
この息苦しさが、オーガズムの訪れの前触れであることを。
「はっ、あっ…ダメっ、もうイクっ…!」
誰に言うでもなく、囈言のように、鼻にかかった艶かしい声でそう溢しながら、極上の悦びを得たい一心で指の律動運動を続けた。
すると、腹部から何かが迫り上がり、それが爆発したかのように、小麻知の全身を閃光が瞬時に駆け巡った。
「ひっ、あっ、はぁんっ…!」
その後、まるで時が止まったように、手足の指先から頭の天辺まで全身の動きを一瞬だけピタリと静止させると、彼女は短く控えめな声を上げて、悦びの頂点に上り詰めた。
視界も思考も閉ざし、小麻知は全身を包む浮遊感に酔った。
「あっ、はぁっ、」
数分、或いは数十秒の筋肉の硬直が解かれると、無意識に止めていた呼吸も再開させた。
瞼を開け、はっきりと意識を取り戻すと、今度はじっとりした火照りが、彼女の肌に纏りついた。
小麻知は、シーツを湿らせるまでにずぶ濡れになった、秘口から指を抜き出した。
待ち望んだ瞬間を迎えたが、小麻知の淫事はまだ終わりではなかった。
後処理をしないまま、彼女は近くに置いた馴染みのアダルトグッズを、自身の欲情を浴びた指で握った。
太くて大きめの男性器、振動やうねりも自在…バイブだった。
静止状態のそれを局地へと持っていくと、小麻知は先程まで指を埋め込んでいた場所へと当てがった。
「あうっ、」
最高潮の悦びを得た内部は敏感で、異物の侵入を認識すると、不規則で間隔の短い収縮を見せた。
熱い疼きに甘く悶絶しながらも、彼女は押し当てていただけの無機物を、奥へゆっくりと進めた。
興奮の絶頂を迎えた余韻が未だ残る中は、淫蜜で潤っていて、ズブズブと引っ掛かる事なく、挿入物を飲み込んでいく。
「はあっ、あぁんっ…あぁぁんっ、」
血も体温も通わないが、最奥を突き刺す火傷にも似た熱さや、挿入物に膣壁が馴染んで絡む、一体感を連想させるには充分だった。
しかし、最上の悦びを一度得た心身は、小麻知の内に眠っていた、潜在的な欲求を呼び起こした。
男の肌を欲して
(本物なら、もっと気持ち悦いだろうな…)
それは紛れもなく、生身の男性との交わりを望んだ、肉体的な欲求。
そんなの馬鹿馬鹿しいと、いつもなら意地を張って頭から振り払うが、理性が薄れてる今、それは叶わなかった。
恥も外聞も捨てた、素直な気持ちを無自覚に抱いたまま、小麻知は咥え込ませた淫具のスイッチを入れた。
籠った機械音が、微かに彼女の聴覚を刺激する。
「ひぃっ…はっ…あぁぁっ、」
最大強度の振動は、聴覚とは対照的に、子宮口を鮮明に刺激し、小麻知の漠然とした願望を満たしていく。
そのまま、ゆっくりと抜き差し、先端で弱く突き上げた。
「あっ、あっ…あうっ、」
(…もっと気持ち悦く)
振動に加え、抽挿を始めてみるも、男の肌を欲し始めた心身を満足させるには、程遠かった。
(誰か、誰か…もっと私に快楽を)
より淫らな熱を求めていると、ある事が頭を過った。
心身共に満たされない貴女に極上の悦びをお約束します
これ以上の快楽を求め、頭の中で縋ったのは、外で浮気する冷たい夫ではなかった。
名前も性格も解らないが、確かなテクニックを持っているであろう、プロの男性。
(これでイケなかったら…試して、みる?)
自問自答すると、小麻知は律動を速め、強い摩擦を作り出した。
「あっ、あっ、あっ、」
最初のクライマックス目前時と同様、大きな何かが迫り来る感覚が、彼女に襲いかかる。
体温が急上昇すると同時に、それが中心部に全て集中した。
全身からエネルギーを与えられた、蜜口や蜜壁が、収縮や予測不能なうねったりと、ぎゅうぎゅうと異物に密着する。
「あっ…はっ、」
肢体は熱くなっても、スッと冷めていくのに対して、活発で淫靡に動く秘部は熱を持ち続けるという、上下で正反対の感覚に、小麻知は官能的な声を上げながら、またこの上ない悦びを予感した。
それを手繰り寄せるよう、彼女は畳み掛けるように、振動を継続させたまま、抜き差しの動作を限界まで速める。
「あっ、あっ、あっ、…はぁんっ、またっ、またっ、」
しかし、位置がズレたのか、或いはリズムや強さが僅かに乱れたのか。
いくら奥をガツンガツン突き上げても、興奮の絶頂に上り詰め、小麻知の心身が至高の悦びで満ち溢れる事はなかった。
それどころか、摩擦熱によって生み出された疼きが全身を巡り、頂に到達できそうで出来ない、焦らされている状態に陥った。
(このままじゃ終われない…!)
雑念を抱えながら、小麻知は躍起になって子宮口付近を突き続けた。
「はぁっ、はぁっ、…はぁっ、」
だが、筋肉の疲労が限界に達し、動かしていた腕をとうとう止めてしまった。
身体的にも感情的にも、最後の律動にスパートをかけていた為に、全ての気力を使い果たした小麻知は、振動を止めて挿入物を抜き出した。
中途半端でもマスタベーションを終えると、肉体の興奮が鎮まり、薄れていた理性が取り戻される。
未知の体験への不安を期待を秘めながら
「…オモチャ使ったのに、イケなかった」
余韻で秘処が細かく痙攣するのを感じながら、小麻知は力なくどこか他人事のように呟いた。
初めての経験に、全身に不完全燃焼な熱を残したまま、ただ唖然とした。
“悔しかったら、浮気の1つくらいしてみろ。勇気がないお前には到底無理だろうがな”
彬の言葉が頭の中でこだまする。
美しく揶揄される“セラピスト”と呼ばれる男は、いわゆる“風俗嬢”と同じだろう。だが、相手がどう思っているかなんて関係ない。
しばらくの間、身動き1つせず、ぼんやりと考えた後、彼女はおもむろにスマートフォンを手に取り、発信履歴からまだ1度もダイヤルしてない番号を画面に表示させた。
いつもなら、ダイヤルボタンをタッチするのを躊躇ったが、今日は指を微かに振るわせながら、意を決してダイヤルし、聞き口を耳に当てた。
コール音が数回で途切れる。
「もしもし…」
そう口にする小麻知の声には、緊張や迷いが僅かに感じられた。
生身のぬくもりから得られる恍惚としたエクスタシー、絶頂アクメに期待を寄せながら…。
(PR)