捨てられた花嫁の足コキとセックス 最低の官能を味わった男の憂鬱

「ちゃんと来てよね、招待してあげるんだから」
上から目線で、それでも満開に咲き誇る花の様な笑顔を浮かべ、招待状を差し出してきたのに何て体たらくだ。
ーオレは、笑顔や幸福感で一杯の鞠亜の晴れ姿を見に来たんだ
ー20年抱き続けた鞠亜への未練や恋情を断ち切りたくて招待状を受け取ったんだ
そう思うと、純白のウエディングドレス姿で、招待客1人1人に頭を下げて回る鞠亜に、どうしようもなく憤りを感じた。
「舐めてなぐさめて…」慰み者にされた男
「慰めてよ。結婚式で新郎に逃げられた、可哀想な私を」
結婚初夜を祝って、新郎と味わうはずだったスパークリングワインを、ほぼ独りで飲み切ると、鞠亜は頬に天然の頬紅を施し、陽気な口調で言った。
「慰めろって…もっと具体的に言え」
理解不能な素振りで掘り下げると、彼女は声のトーンを変えないまま答えた。
「じゃあ、跪いて私のココ、舐めて」
そう言うと、鞠亜は自らの手でスカートを捲り上げ、その下のショーツをずり下げると、黒い茂みに覆われた女性器を、オレの眼前に露にした。
***
「あっ、はっ、…そうっ、そこっ…あはんっ…」
オレの旋毛に向かって喘ぎ混じりに発せられる、鞠亜の甘く熱っぽい声が、鼓膜を振動させる。約20年恋焦がれていた相手の、秘めた部分を味覚で堪能し、性的な興奮や歓喜で満たされた。
更なるそれらを欲し、舌を限界まで伸ばし、より奥の肉壁へチロチロと舌先を這わせる。
「ひっ…あっ、あぁんっ!」
入り口付近より熱く湿る肉壁に舌先で触れた瞬間、先程とは明らかに違って鞠亜の声が甲高くなると同時に、ベッドの軋みも大きくなった。そんな変化に加えて内壁の裏側の腺を刺激し、液体の分泌も促されたのか、咥内に収まり切らなかった液体が、オレの口角から顎を伝ってシーツを湿らせる。
(…奥が好きなのか)
漠然と考えながら、聴覚と味覚で鞠亜が乱れていく姿を感じ取っていた時だった。
「…っ!」
局部にぶら下がる肉の塊へ、鞠亜の素足が置かれた。
捨てられた花嫁の足コキの官能
花嫁姿の鞠亜は、置いているそれに力を含ませると、意思に反し、硬さや熱を孕んだ肉を踏み始めた。
鞠亜の足は女特有の、小ささや繊細さがあり、見た目は上品だが、それと裏腹に足癖はかなり悪かった。
足は力を持ったまま、円を描くように動き、オレの硬肉へ衝撃を与えた。
「ふっ…はっ、」
下腹部だけで止まっていた熱や、疼きがゆっくりと全身を巡る。
「足で踏まれて気持ち悦いんだ?…硬くなってる」
本能に忠実なオレを揶揄しながらも、鞠亜は、動かす方向を逆転させたり、止めたりと、様々な形で足を動かし続ける。
結婚するはずだった新郎か、その前まで付き合いがあった男に覚えさせられたのか。鞠亜の足は男の体を熟知していて、性に関しての経験値が低いをオレを快楽の坩堝へ突き落とすには充分だった。
やがて、限界まで硬さと質量を孕んで隆起も大きくなり、最終的に小さな足の下では収まらなくなった。
花嫁姿の女に衣類の上から足で攻められる情けさとどうしようもない快感
(まるでM男が喜びむせる、抜けないエロ動画のワンシーンみたいだ…)
「これ以上続けたら、パンツ汚しちゃいそうだね」
そう言いながら、鞠亜はどうしようもない疼きに悶えるオレの醜態を見下ろしていた。
確かに彼女の言葉通り、このまま踏まれ続けたら、衣類にまで及び、まるで失禁したかのように見える。それはできるなら避けたい、ジワジワと沸き起こる吐精感を紛らすように、眉間や腹筋に力を込め、与えられる刺激に耐えた。
しかし、そんなオレの足掻きを嘲笑うように、鞠亜は足を動かし続けた。
「っ…っ、」
クンニリングスしていた舌の動きが止まる…。
先程までは何も感じなかった、インナーの生地が肉の表面に擦れる些細な刺激ですら、切迫した今のオレにとっては、目を反らせない程に鮮明で強烈に思えた。
(ダメだっ…もうっ、)
もう後始末しよう、抑え切れない熱に心中で密かに白旗を上げ、快楽の海に心身を堕とそうとした時だった。意思を持って隆起物の表面を彷徨っていた足が、眼下から姿を消した。
幸か不幸か、慈悲か無慈悲か。衣類を汚さず大人の男として体裁は守れたが、寸止めを喰らい、楽な状況でない事実は変わらなかった。
「そんな生ぬるい刺激じゃ、私はイケないよ」
下手くそ、捨て台詞のようにそう最後に言い放つと、癖の悪い足はオレの肩を蹴飛ばし、自身の局部から体を引き剥がした。
空っぽの悦び
「後は自分でやるから、コンドーム着けたらベッドに横になって」
吐き捨てるようにそう言うと、鞠亜は袋に入ったそれを1つ、オレの隆起物に向かって投げ付けた。
ちらりと視線を上に向けると、口角で浅く緩やかな孤を描いて、虚無的だが妖し気な笑みを浮かべる彼女の顔が視界に上部に映る。その表情から、鞠亜の心情は何も読み取れそうになかった。
そんな自分の無力さにギリッと奥歯を噛み締めながら、オレはスラックスのファスナーを全開にし、最後の砦から隆起物を取り出した。すると、2枚の布の窮屈さからの解放感を堪能するように、赤黒い肉の棒はフルっと勢いよく揺れて天井を向いた。
自らで招いた卑猥な光景に羞恥や嫌悪を抱きながらも、正座している脚を少し広げ、ピリッとビニールを破いて中身を取り出した。オイルの滑りに苦戦しながら、尚も天井を見上げ続ける肉の屹立に、ゆっくりと薄いゴムを被せていく。輪を付け根の部分まで下ろしてから、言われたままベッドへ仰向けに寝転がった。
「言う通りにしたぞ」
すると、鞠亜は表情を崩さないまま、オレの半身に跨ってきた。
重力に従って、撓わに揺れる柔らかそうな肉の球体が、赤く色付いた豆粒ほどの肉尖部が、オレの欲情をより一層煽った。指の跡が残る位に強く、滅茶苦茶に揉み解きたい衝動に駆られたが、意地やプライドを捨て切れず、ギュッと強く拳を作って堪えた。
しかし、そんな行為は無駄に過ぎなかった。
「触りたいでしょ? いいよ、好きなだけ触って、怒らないから」
拳を握って理性を繋ぎ止める従順さを挑発するよう、鞠亜は垂れ下がった膨らみの先でピンと芯を持って立ち上がる乳首や、その周辺の乳房でオレの頬を撫で回した。
男とは違う先端部の硬度や温度、頬を撫でる適度な潤いを持った滑らかな肌、仄かに漂う香水とは違う甘さを孕む鞠亜にしかない香り。それらが、慰み者らしく従順で居ろと言われているような無言の圧力だと理解していても、眩暈がする程の肉欲を覚えずにはいられなかった。
「…イキたいんだろう? だったら、さっさと挿れてイって終わらせろ。オレは明日、予定があるんだ」
「イキたいのは史也も同じでしょ?」
相変わらず笑みを浮かべたまま言うと、鞠亜は上半身を起こすと、天井を向いたまま屹立と垂直になるよう、秘処を移動させた。
そして、そのまま腰を落とした。
「あぁぁんっ…!」
薄いゴム越しに亀頭部で滑りと熱さを感じ取ったと同時に、一際甲高く甘い鞠亜の嬌声が部屋中の空気を激しく振動させた。
「…史也も、ちゃんと男なんだね…夏樹と一緒で史也のも太いし、硬いっ」
「…何バカな事、言ってる、」
「そう、だねっ…ゴメン、」
今まで崩れなかった笑みを少しだけ壊し、眉間に皺を刻んで瞼をギュッと閉じると、彼女は後ろに両手を着いて肢体を支えたまま、下腹部だけを器用に動かして、収まり切ってない陰茎をゆっくりと中へ埋め込んでいく。
解っている…1度として、鞠亜がオレを1人の男として見てないのは。
しかし、こんな状況になっても、強がって甘えてもらえないのは、悔しくて酷く癪に触った。
「ふっ…はっ…、」
予想以上の大きさだったのか、唇から零れる呼気は短く乱れていて、艶めかしさや甘ったるさよりも息苦しさを色濃く窺わせていた。挙句には、硬く閉ざされている瞼の隙間から透明な雫を一粒ずつ溢し、未だ赤みが残る頬に筋を作る始末だった。
(…無意味だ、こんな痛みしか生まない行為は)
しかし、そんな気持ちも、中断するのもオレの独りよがりでしかない。
「…鞠亜っ、」
(ダメだ、独りよがりを押し付けたら…断らなかった以上、最後まで付き合うんだ)
大きくなる衝動を圧し潰すように、オレの上で淫らに動く幼馴染の名前を口にした。しかし、いつの間にか屹立を全て自身の内腹へ咥え込ませた彼女から、応えは返って来なかった。
「どうしてっ、来てくれなかったの…夏樹っ」
オレを通し、その男の姿を見ているのか、重ねているのか、少し乱れた声調で問うと、鞠亜は下半身をゆるゆると上下に動かした。
優しい痛み
「私の何がっ、ダメだったの? …何でっ、何も言ってくれなかった、の…!」
今はここに居ない男へ当て付けるように、声を荒げて語尾を強調すると、それをそのままぶつけるように、結合部の動きも加速させた。
鞠亜の動きに合わせ、胸元で上下に揺さぶられる、色白い肉の球体。抽挿の度にチラチラと肉茎が覗く様子。艶かしい喘ぎと共にオレの上で、淫靡な踊りを見せる華奢な裸体。
結合部で鈍く響く2種類の欲が混ざり合う音、高い体温で濡れた蜜肉にピタリと絡まれる感触。
生殺しを喰らい、些細な全てが欲情を煽る要素になり得る筈だが、少なくとも肉体は悦楽を享受している筈なのに。性の悦びに忠実な肉体に反し、精神は冷めていく一方だった。
何故なら…
「あっ、あぁんっ…イキたいっ、イカせてっ…貴方のっ、熱いのでっ…!」
縋るように言葉を紡ぐ鞠亜の心情も、オレと同じに見えるから。
(…もうっ、付き合い切れない)
「鞠亜っ…!」
半身を起こして細い手首を掴み、彼女の肢体を胸に抱き寄せ、体勢を逆転させた。
「いぁっ、何っ…いやっ、やだっ、」
そして、雑念だらけの不安定なリズムを中断させ、今度はオレがそれを刻んだ。出発から、最奥をガツンと強く貫くよう、これ以上ない程に激しく大きく。
「やだっ、やめてっ、…痛いっ、痛いっ、」
「悔しいんだろ! 泣きたいんだろ! 」
「やっ、あっ、あっ…」
「だったら、こんな回りくどいやり方せず、そいつに直接怒りをぶつけろ! 泣きたいなら強がらず素直に泣け!」
動きに内壁が馴染み切れず、痛みを感じる鞠亜を尻目に、オレは精の解放を目指して、彼女の両側に手を着き、更に強く腰を打ち付けた。
「それがお前だろ! 黒崎鞠亜っ!」
「やっ、やめてっ、…史也っ、やめてっ、」
痛みを与えたかった訳じゃないのに、泣かせたかった訳じゃないのに。ただ、笑って欲しいだけなのに、幸せになって欲しいだけなのに…鞠亜に一際強く締め付けられ、オレは避妊具の中で呆気なく精を吐き出した。
目的を果たした瞬間、冷え切った精神に共鳴して、蜜路の中で屹立が、ふにゃんと柔らかい肉塊に戻っていくのが解る。
「はぁっ、はぁっ…」
「…うっ、ううっ、」
オレの乱れた浅い呼吸に混じって、鞠亜の啜り泣く声が部屋の空気を揺らして。
それが感情発散の皮切りとなったのか、静かな啜り泣きが、声が入るはっきりした泣き声にやがて変わった。
確かに、泣けとは言った。
だが…
(泣きたいのはオレの方だ…)
やり切れない、行き場のないそんな感情を胸中に秘めたまま、オレは幼子のように泣きじゃくる鞠亜を黙って見詰めた。
(PR)
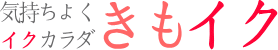
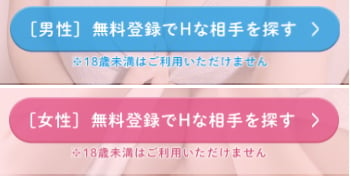













スパークリングワインを一気に飲み干したので、それが鞠亜の身体を巡って最終的に“下腹部”に集中し、二回戦目でウェディングドレスを黄色く染める、という展開はございませんでしょうか。