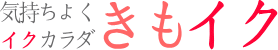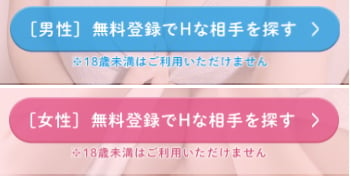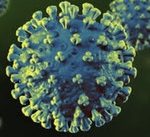新婚初夜の涙

新婚初夜の涙
誓い
「結婚おめでとう」
4年ぶりに再会した司が私にかけたのは、最も彼らしく秩序正しい言葉。
―全てを幸次に捧げないと
新婚初夜、交際中は何となく避けてきた、彼とのセックスを解禁すると、プレッシャーにも似た気持ちが私にのしかかる。
「こんなに勃たせて…可愛い」
意地悪く言われると、胸の辺りを濡れた感覚が刺激する。
背けていた顔を正面に戻すと、幸次が私の膨らみ頂点にある突起物を、舌先で弾くような軽いタッチで舐めていた。
完熟のサクランボみたいに色付いた小さな勃起物が、眼下で他人の舌に弄ばれる様は、咥内で弄ばれるより私の視覚を刺激した。
片方は舌で、もう片方は2本の指で挟まれて転がされる。
「っ、」
気紛れに短い爪先で弾かれると、全身に鈍い震えが走って、局部がじんわりと疼く。
その感覚が堪らず黙って受け取れなくて、私は両方の脚をゆっくり立てて身動いだ。
焦らず身も心もゆっくり昂らされる感覚は思いの外、心地が好い。
(…物足りない)
でも、目眩く官能を欲しているのも事実だった。
壊れ物を扱うような、処女を抱くみたいな、こんなゆっくりしたセックスを私は知らない。
私の気持ちなんて粗末に扱ってくれて良いから、もっと自分の欲望を優先してよ。
「幸次」
胸元で動く彼の頭上に向かって名前を呼んだ。
「どうかした?」
「ずっとお預け喰らわせたお詫びに、今日は私がご奉仕してあげる」
彼は驚いたように一瞬目を丸くしたが直ぐに屈託なく笑うと、”じゃあ、お願い”と答えた。
葛藤とエクスタシーの狭間
私は、横になった幸次に背中を向けて引き締まった腹部に股がり、体重を預けた。眼下の下半身に上半身をくっつけ、顎に下生え特有の硬さを感じつつも、柔らかい芯を持つ肉の塊を咥内に収めた。
自分の咥内を膣に見立てて、収めた肉に舌を擦り付けながらゆっくりと出し入れする。
甘い汁でも舐め取るように、ねっとりと下から上へ程好く潤う陰茎を舐め上げる。
舌を這わせた部分に間接照明が反射して、そこからヌラヌラと光を放つ様は、何とも淫靡だ。
全体が妖しげな光で煌めく時には、幸次の昂りはしっかりと芯を持って、太くて硬い棒と化した。
“愛梨だけだよ。僕をこんなに興奮させるのは”
天井を向いた幸次の昂りを目にしていると、司のそんな言葉が脳内で再生された。
司の性器を唇や舌で刺激して挿入して、彼が射精したらそれで終わり。キスも無ければ私への愛撫は殆んど無い、端から見たら司主導の粗雑なセックス。
でも、最中に見せる、涼しい表情が唯一崩れるその瞬間が私はすごく好きだった。
彼とのセックスを振り返っていると、腰の辺りを持ち上げられて一瞬体がフワリと浮いた。
気付くと、私は幸次の顔の上に股間を近付ける体勢にさせられていた。
体勢を崩そうとするも時既に遅く、腰にがっちり回された腕で固定された。
「オレも愛梨のエッチな場所舐めたい」
幸次の嬉々とした声の後、局部を熱く濡れた何かが這う。
それが彼の舌だと理解するまでそんなに時間はかからなかった。
「やだっ、そんなとこ舐めたら…」
26年生きてきた中で性器を舐められた事なんてなくて、あまりの羞恥に居たたまれない気持ちになり、細い声で言った。
「ほら、愛梨も口動かして。止まってるよ?」
そんな私の言葉なんて聞くつもりないとでも言うように、幸次は再び私の局部に顔を埋めた。
羞恥を少しでも紛らすように、目の前の昂りを握り、亀頭部から入る分だけを口に含んだ。
限界まで膨らんだ陰茎、滑らかで分厚い肉笠、熱い欲液を滴らせる吐精口に舌や唇で触れて、入り切らない部分は手で皮膚を上下に擦り上げる。
指先や唇でも感じ取れる位、陰茎に張り巡らされている血管にはドクドクと激しく脈が循環している。
昂りに刺激を与える間も、私の下半身では彼の舌が縦横無尽に動く。
火照って膨れた肉唇の先にある、核心的な部分を舌や唇で触られれば、どうしようもなくそこが疼いて下半身の力が抜けそうになる。
「はぁっ、ぁっ、」
蕩けるような熱に乱れた呼気を溢しながら、砕けそうになる腰に力を入れて肢体のバランスを保つ。
すると、そんな私を嘲笑うように、幸次の舌の動きが激しさを増す。
結合口を掠めるだけだった探るような動きが、舌先を尖らせて突っ付いたり舐め上げたりと、無駄の無い動きに変わる。
「あっ、あぁぁっ…!」
普段より何オクターブも高く艶かしい声を上げて、甘くも強い疼きに悶えた。
私の反応に気を良くしたのか、幸次の動きは止まらない。
彼の唾液に混ざって、私の内壁から溢れ出る液体が、ジュルジュルと舐められたり吸われたりする音が立って羞恥と扇情を煽られ、唯でさえ上がっていた体温がまた上昇した。
「あぁぁんっ…」
「すごいトロトロ。吸っても吸っても、出てくる」
言われると、舌や唇に加えて指も入ってきた。
彼の言う通り、私の入り口はグズグズに濡れている上、周りの筋肉も熱を持って解れ切っていて、2本の指も難なく受け入れた。
「あっ…!」
頼り無かった舌や唇に指の力が加わって、薄くかかっていた霧が晴れたような、はっきりとした疼きが私の心身を巡る。
「あんんっ、」
腰に回っていたもう片方の腕が離されると、今度はその指先が潤う入り口の上にある小さな粒に触れた。
ドロドロに溶け切った中は、イヤらしい音を立てながら、舌と少し曲げた爪先や関節で内壁を擦られ、外では小さな突起物を指の腹でグリグリと弄り回す。
「あぁっ、あぁぁんっ! ダメっ、やだっ、おかしくなっちゃうっ…!」
思考から体の自由まで全てを奪われるような凄まじい官能に、悲鳴にも似た喘ぎを溢し、肢体をエビのように縮こませて悶絶した。
司とのセックスでも味わった事のない未知の感覚は、私にとって悦びではなく恐怖でしかなかった。
無意識に目頭も熱を持ち、私の瞳からはポロポロと涙が溢れ出す。
“イクなら、僕がイった後にして”
司のその言葉を思い出してしまった私は、残っていた僅かな体力を総動員させて、幸次の半身からベッドに体を預けた。
「はぁっ、はぁっ、はぁっ、」
喘いで急激に乾燥した喉で呼吸を繰り返しながら、私はベッドに預けていた体をゆっくり起こして、彼の方を向いた。
そして、半身を起こす幸次の腹部に手を着いて顔を寄せた。
私の分泌液で唇を煌めかせて、キョトンとした表情の彼と視線を合わせた。
「…イクなら貴方の、この硬いのが、いい。これで私の事、メチャメチャにして?」
知られたくない気持ち
言葉の節々で咥内の唾液を飲み込んで喉を潤しつつ、幸次の昂りを手で握って懇願してから、再び彼の下腹部に股がり、少しずつ腰を下ろしていく。
「はぁぁっ…!」
グチュっと音を立てながら、彼の怒張が私の中に埋め込まれる。
しっとり濡れて拡がったそこは、初めて司の異物以外を受け入れたにも関わらず、彼に挿入された時と違って全く痛みを感じなかった。
痛みを感じないのを良い事に、私は亀頭冠から一気に全てを内壁に収めた。
「はぁっ、ぁっ、」
「オレ、すごい幸せ。こうして愛梨の中に入れて、1つになれて」
“少しでも長く愛梨の中に居たいから”
耳元に届く幸次の熱い囁きが、司のそんな言葉を思い出させた。それは私が不意に問いかけた疑問に対する司の答えだった。
その時の彼の真剣な眼差しは、今でも私の頭に焼き付いている。
司との思い出に浸っていると、いつの間にか、背中には布団があって、眼下の幸次の顔が上にあった。
「愛梨、オレを選んでくれてありがとう」
そう言って、彼は屈託ない笑みを浮かべた。
でも、その笑顔はいつもと違って切なげで、私の気持ちを全て見透かされたような気がした。
今の私はどんな顔をしているのか。何も考えさせないと言わんばかりに、幸次は挿入した昂りを動かした。
「はぁっ…あぁっ!」
濡れ肉の路の手前と最奥をゆっくり往復しながらも、内壁の至る部分を抉るように突き上げる。
「あぁぁんっ!」
幸次の昂りのどの部分かが私の内壁を掠めた瞬間、さっきと同じ思考を切り離されそうな濃蜜な官能が全身を再び巡った。
何とか意識を繋ごうと、肢体をうねらせながらもシーツを強く握る。
「っ、すごい締め付け…ずっと、してなかったでしょ、セックス」
得体の知れない感覚を味わわされて喘ぐ私とは反対に、彼は締め付けられる感覚に悶えながらも、余裕ぶって笑みを浮かべて軽口を叩いてきた。
「もっと愛梨の中じっくり味わいたいし、優しくしたいけど…ゴメン」
降参したように笑顔を歪めてあっさり虚勢を崩すと、幸次は埋め込んでいる昂りの位置を合わせるように下肢を少しずつ動かした。
「んっ、」
彼の先端が当たり、官能の余韻を刺激されたようにズクッと体が疼き出した時だった。
「あぁぁぁっ!」
先程の助走を着ける準備運動のような動きとは対極的な、激情を余さずぶつけるような激しい突き上げが、私の心身に悦楽を一気に駆け巡らせた。
律動的な摩擦のせいか、幸次を受け入れている部分が焼けただれそうに熱い。
「あんっ、あっ、あっ…あんんっ、そんな動いたら、私のアソコ、焼けちゃうっ…!」
幸次の動きに合わせてギシギシと軋むベッドが、私の甘ったるい声に混じる2人分の乱れた吐息が、結合部で立てられる淫らな水音が、私達の劣情を駆り立てては更なる官能へ導く。
そのせいか、動き続ける幸次の昂りがドクッと質量を増して、私の中でピッタリと隙間なく密着した。
「…貴方の熱いの、いっぱい私の中に出して…」
我慢に我慢を重ねていたのか辛抱強くないのか、私が言ってほぼ同時だった。
幸次の律動が止まった後、熱い迸りがドクドクと流れ込む感覚がしたのは。
幸次の射精を煽ったのは私。
“僕以外の男とセックスしたら、君はもう赤の他人だ”
結婚を決めた時から、もう司との関係を戻せないと解っているつもりだった。
それなのに、彼の言葉を思い出したら涙が止まらなかった。
泣きじゃくる私に向けられる幸次の視線を、瞳へ繋げる勇気はなかった。
(PR)