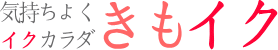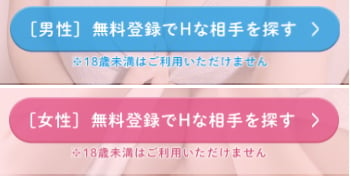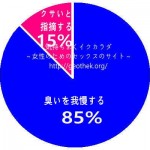射精された白い欲と絡まる愛液~情事のあとも責められて~

白は綺麗なものの象徴で、美しいものの象徴である。
じゃあお腹の辺りに吐き出された彼からの白い欲は美しいのだろうか、と視線を下にやった。
ベッドで仰向けになる私のへそのあたりにちょうど彼の頭があり、私が目線を向けるために顔を動かしたのを察してか、彼もこちらをに目をやる。
視線と視線が間接照明のオレンジの中で絡みついた。
塗られるのは精液か欲か
「……きもちかった?」
そうほほ笑む彼の表情は、会えないときに見る写真と同じなのに何でこんなにも……。
「ひゃ、や、」
「やじゃないでしょ」
もう達して全部済ませたはずなのに、彼は私のクリトリスをとんとん、と叩くように愛撫している。その表情はとても満足そうだ。
「いった、ばっか」
「イったばっかだからこうしてるんでしょ」
今度は肉芽をぐにぐにと潰すように弄ぶ彼に、普段のように悪態なんかつけるわけがなく、ぎゅ、と身を縮め快感に流されるしかなかった。
「やだ、ねえ、もう、いったから、」
「うん、イったね」
愉しそうに喉仏を上下させ、彼は私のお腹に吐き出された精液を指に絡めた。
「ごめんね、汚しちゃって」
何を今更、と私は彼から目を背けた。
汚しちゃって、なんて今更なのに。あなたに汚されるのなら私はいくらだって喜んで汚れるのに、そんなことも分からないなんてなんてあなたは馬鹿なんだ、とため息ともこぼれた吐息ともわからないそれが少しだけ開いた唇から出ていく。
「……ねえ、考え事してるんじゃない?」
随分余裕じゃん、と呟いた彼は、指を先程まで彼の性器が入っていたそこに、ぐ、っと挿入した。
「ひゃ、」
「まだひくひくしてる、淫乱なの?」
達した後クリトリスいじられて中に指を挿れられたらこうなるに決まってるのに、内心つっこんでみるがそんな気力があるわけがなく。抵抗するのも疲れた私はただただ押し黙って不満を晒した。
「嘘、かわいい」
……調子が狂うのだ。こういう時だけ素直だから。
底無しの性欲、再び絶頂
「ねえ、いつになったら中に出せるのかな、早く結婚したい、そしたら俺の赤ちゃん身ごもってくれる?」
「んぅ、」
「ごめんごめん、冗談だよ、結婚したいのは本当だけど、」
ずっと語り掛けていても、快楽で訳が分からなくなっている私の返事が曖昧でも、彼の手は止まらない。
「お前のここから俺の精液出てきてるところ見たら、俺興奮してどうにかなっちゃいそう、試していい?」
「え?」
彼のごつごつとした指は私の腹部の白をすくい、それを私の膣に入れてはそれを内側の壁にこすりつけていた。
生ぬるい、明らかに自分の体液ではない液体が自分の中に馴染んでいく感覚に背筋がぞわりとして、身震いしてしまう。
妊娠してしまうかも…という恐怖心が、輪をかけて快感を上昇させる。
感じちゃってるのめちゃくちゃ可愛いんだけど、と何度か掬って塗ってを繰り返していた三本の指で愛撫を始めた。
「ひゃ、」
「ここきもちいんでしょ?」
さっきよりも強い力で、指の関節を使いながら一番敏感な所に押し当ててきて、声が我慢できない。
内側に塗られているのはただの精液なはずなのに、それがまるで媚薬みたいに熱いような気がして、声が抑えられなかった。そんな私を見る彼は至って満足そうだ。
「や、ぁ、」
きゅう、と中が締まる。いきそう、それを察した彼の口が弧を描く。
「いっていいよ、見ててあげるから」
「っあ……あ……!」
三本の指はばらばらに、それでいて私の気持ちいいところを的確に刺激する。
それにこたえるように膣は指にビクビクと指にまとわりついてしまう。浅いところ、Gスポット、そして奥深いところまで丁寧に刺激されて私は訳が分からなくなってしまっていた。
私の身体が弓形になりそうなのを見た彼はここぞとばかりに三本の指を一気に奥に差し込み、まるで男性器がピストンをする様に激しく抜き差しを始めた。
「イッちゃう……!」
「ねえ、これがおちんちんだったらな、早くここで俺の、出したい」
「ひゃぁ……や、っ……!」
一番奥で指を細かく動かされたらもうダメだった。
彼の指が撫でる膣から背筋を伝い快感の波が身体を襲う。ビクビクと震える身体も奥で蠢く指も、まだ止まることを知らない。
さっきも散々彼に情欲をぶつけられて絶頂してしまっていたのに、またイってしまった。
「イッちゃったね、ほら、中出ししたらさ、きっとまだここで俺のがびゅくびゅくしてるんだよ」
中出しごっこの成れの果て
これじゃあまるで中出しごっこだ、と肩で息をしながら結局耐えきれなかった快感の余韻に浸る。どうやら満足した彼は、ゆっくりと、そしてわざと私のいいところを刺激するように指を抜いた。
「ぁっ、」
「また感じちゃった?もしかして足りない?」
「!そんなわけないでしょ、バカ!!」
「冗談だってば、怒らないでよ」
続きはまた今度ね、と彼は微笑んだ。
続きがあるのか、と考えるだけで疲れるような、それでもまた与えられる快感への期待でじっとしていられないような、なんとも複雑な感情に襲われる。きっと今の私は事後なのも相まってかなり微妙な表情をしているだろう。
「ねえ、見える?」
彼は私の目の前に先ほどまで私の恥ずかしいところを乱していた指三本を持ってくる。そこには、私の愛液と絡まった彼の精液がべっとりとついていた。
恥ずかしくて目を逸らすとごめんごめんと彼は笑って私の横に寝っ転がってくる。
「意地悪しすぎちゃったね、でもめちゃくちゃ興奮した、俺がお前を汚してると思ったら歯止めきかなくなっちゃった。ごめんね」
ごめんなんて言ってもきっとまた同じことをしてくるのは目に見えているし、私は止めもせずその快楽に身を任せることも分かり切っていた。
男の人は女の純潔を奪うことを汚すなんて言うけれど、私は確かに白に染められていた。
それが汚れているかなんて私には一切見当もつかない。
乱れる私をただただ満足そうに見つめる彼に目覚めたら何と悪態をついてやろうかと、そっと目を閉じた。
(PR)