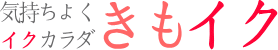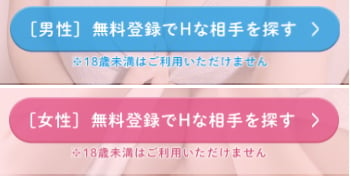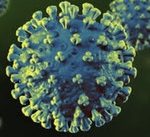友達と恋人 Vol.2

冷たい官能
ー美雨という恋人が居るにも関わらず、中学の時から恋い焦がれていた蓮夜とセックスした
その事実は、この上ない幸福を与えたと同時に、美雨への罪悪感を煌太に与えた。
蓮夜と閨を共にした日以来、煌太は美雨の顔を上手く見られないでいた。
「煌太」
美雨の家のリビングで彼女が戻るのを待っていると、当の本人に名前を呼ばれて、煌太は反射的に振り向いた。
「!」
声がした方を見ると、彼は驚きで思わず息を飲んだ。振り向いた先に確かに美雨が居た。だが、そこに居たのは一糸纏わぬ姿の彼女だった。
「おいっ、なんて格好してるんだ…!」
「あ、やっと私の事を見てくれた」
突然見せられた女の裸を前に、焦って慌てる煌太と反対に、美雨は面白い物でも見たように笑って言う。すると、彼女は今の姿のまま煌太にゆっくり迫る。
「…早く、服を着ろ」
全裸で気まずくて気恥ずかしいのか、煌太はまた美雨から顔を反らして、ボソリと小声で言った。そんな彼の隣に腰を下ろすと、煌太の肩を掴んで自分の方に向かせた。
「…何で、私を見てくれないの?」
言葉を投げ付ける美雨の声色、強い口調とは反対に頼りなくて、泣き出しそうにも聞こえた。
「…好きな人でもできた?」
彼女のその問いに、煌太は図星を突かれたように、びくりと肩を振るわせた。
「そんなの、許さない…!」
確信も真実も遮るように言うと、美雨は心身に出来ていた煌太との距離を埋めるように、彼の唇に自分のそれを重ねた。薄いけど柔らかい彼の唇が、コーラルピンクの口紅が引かれている、ふっくらと厚い唇を余す事なく受け止める。
煌太の唇を土台のように使って、美雨は無防備に開かれている、彼の咥内に向かってするりと舌を滑り込ませた。彼女の舌先が、戸惑う彼の舌とすぐにぶつかる。
美雨は煌太の舌を絡め取って、自分の舌全体と絡め合わせた。チュッチュッと唾液が混ざり合う音、舌同士が絡まる音が唇が重なっている部分で静かに響く。
不規則に生じるその音は、彼が”やめろ”と吐くであろう言葉も、呼吸をも奪うような熱烈な絡みの表れだった。
しかし、それだけでは満足できないのか、美雨は煌太の下半身に手を伸ばして、手探りでベルトを外す。
「美雨…!」
だが拘束されていない手で、煌太は彼女の体を引き離して、制止するような低い声で名前を口にした。
しかし、後に退く事などできない美雨は制止など無視して、彼のパンツのファスナーを下ろし、下着の中から柔らかい肉棒を取り出した。
そして、彼女は煌太の手を振り解き、腰を高く上げて彼の股座に顔を埋めると、取り出したぶらさがりを躊躇なく口に含んだ。
美雨は柔らかいそれに丹念に舌と唾液を絡ませる。
1番太さのある真ん中、亀頭が隠れている先端を転がすように弱く、ねっとりと舌を這わせ、全体を唾液まみれにして滑りを良くていった。
唾液が絡む下品な音を立てながら美雨は頭を上下に振り、頬に窪みができる位に強く吸うのと、唇からの出し入れを同時にする。
「…はぁっ、」
柔らかかった陰茎に芯が入り、咥内だけで扱うのがギリギリの大きさになってくると、煌太の口から熱っぽく乱れた呼吸が漏れ出てくる。
煌太と付き合って今年で4年が経つ美雨。その間、両手両足の指の数では収まらない位、彼と体を重ね合わせてきた。
煌太の性感を知り尽くしている美雨にとって、彼を快楽の海に誘い込むのは難しくなかった。
与えられる快楽に抗えない彼を前にしながら、彼女は手持無沙汰だったもう1つの手を、女陰に持っていった。
独り悦がり
少し硬めの下生えから、唇のように肉感的に膨れた割れ目を指先でなぞり、その先に隠れている結合部に繋がる入り口を探す。
「んっ、」
すると、少し湿った空洞に指先が当たった。少しの痛みと、熱く蕩けるような感覚が美雨の全身を巡る。
目的を果たすと、彼女は不思議な感覚を産み出すその部分に指先を突き立てた。今まで煌太だけを一途に受け入れてきたそこは柔軟に開き、美雨の指先を難なく飲み込んだ。
(これが、もうすぐ私の中に入る)
咥内でもう1人の彼を弄びながら、それが自分の中に入って突き上げられるのを想像する。
すると、条件反射のように、美雨の膣壁からサラサラとした淫汁が染み出し、煌太を受け入れる準備を始めた。
指を奥に侵入させる程に増す、甘い痛みと気持ち悦さに背中や、桃のように滑らかな球体を描く臀部を振るわせながら、頭を出した尿道口に濡れた息を吹きかけた。
「っ、」
すると、煌太はグッと息を飲んで、声と共に襲ってきた射精感を抑え込んだ。
2つの布の中で大人しくしていた彼の逸物は、美雨の舌や唇や指先で嬲られた事によって、彼女の咥内では収まり切らない大きさに膨張し、血管が浮き出る位に太く、簡単にへし折れない赤黒い肉の棒へと変貌を遂げる。
変貌したそれは、根元から先端までが神経になったように吐息のような僅かな刺激だけでも敏感に受け取り、悦楽として煌太の足の先から脳までを巡って心身を痺れさせた。
望み通りの反応をする彼の顔を見たまま、美雨は淫らな汁で潤い始めた狭い路に埋め込んだ2本の指を動かした。
「あっ、はぁっ、…んっ、煌太っ」
蜜口が、指の関節の凹凸と擦れて産み出される火照りを味わいながら、呼気混じりに彼の名前を口にして、より深い官能の共有を求める。
自分の指を出し入れして、やっている事はオナニーと何も変わらない。なのに、目の前の煌太の指が入っていると想像したら、一層染み出した彼女の分泌液が、指の付け根から手の甲を伝って、手首からソファに滴り落ちる。
美雨は指を動かしながら、煌太の昂りを咥内から解放した。
蛍光灯の光が反射して、ヌラヌラと光を放つ陰茎部。同じように光を放つ亀頭は痙攣していて、その天辺の尿道口からは美雨の唾液とは違う、ヨーグルトの乳清に似た半透明の粘液が、汗のようにゆっくり垂れていた。
「あぁんっ、悦いっ、悦いのっ、煌太っ…!」
煌太を見ながらのオナニーは、喘ぎが我慢できない程の快楽を美雨に与えた。
しかし、彼女の心身は、自らの指以上に長さと太さを持つ物を欲していた。程好かった指への締め付けがキツくなった事がそれを示していた。
(煌太ので突かれたい、メチャクチャにされたい)
そう思いながら、すっかり天井を向いている彼の昂りを、彼女は快楽に濡れた熱っぽい視線で見詰めた。
沸かない欲情
(煌太が欲しい)
1度自覚したら美雨の欲求はもう止められず、彼女は埋め込んでいた指をずるっと抜いた。そして、座っている煌太の上に股がり、亀頭部を蜜でぬるむ蜜口に宛がった。
すぐ目の前にある煌太の頬に掌を置いて、再び彼の唇を奪って言葉や呼吸も奪おうとする。同時に、上げていた腰を下ろして、宛がっていただけの昂りを中に飲み込んでいく。
濡れそぼる美雨の蜜口は、いつも受け入れている物が入ってきたと言った感じに、キツく締め付ける事もなく、従順に口を開いて中に迎え入れていく。
「んんっ…!」
その感覚に、彼女は唇の隙間から熱や湿りが濃縮された篭った艶声を上げ、官能に肢体を痙攣させた。
恋人だから煌太とセックスするのは正当な事実。
なのに、今の美雨にとってその事実がとてつもなく幸福に思えた。感情と官能が高まり、瞬きと同時に睫毛の隙間から大粒の涙が頬を伝う。
「煌太…好きよっ、」
唇を離すと、ずっと抑えていたかのように彼への気持ちが紡がれる。
だが、煌太はそんな美雨から視線を反らしてしまった。それは、蓮夜の気持ちに気付いてしまった後ろめたさ、彼女の純粋な愛情が見えての行動だった。
そんな彼を良しとするはずのない美雨は、煌太の昂りを半分残したまま、後ろのローテーブルに両手を着いて、腹部に力を入れて腰を上下にゆっくりと動かし始めた。
「はぁっ…あんんっ、」
美雨のGスポットやポルチオに、亀頭冠や鈴口が掠ったり擦れる。その時に生じる痺れるような感覚に、彼女は思わず肢体を突き出した。
強調されるように煌太の眼前に突き出された、肌色の椀型の上の濃紅の乳頭が、彼に触って欲しそうにツンと上を向いて勃っている。
「あんっ…! 煌太、煌太っ…!」
(もっと、もっと煌太が欲しい)
そう思った美雨は、両手をローテーブルから煌太の肩に置くと更に腰を落とし、収まっていなかった部分を自分の中に収めようとした時だった。
「美雨っ!」
煌太が美雨の体を持ち上げて、彼女の中に埋まっていた自身を抜き出した。
「煌太…!?」
彼の行動の真意が読み取れない美雨は、答えを求めるように煌太の名前を呼んだ。
「…すまない…」
「煌太…!」
美雨の呼び止めも空しく、煌太は何も答えず苦悩に満ちた顔で、この場を逃げるように去った。
「何でなのよ…!?」
涙混じりに溢された、怒りにも似た彼女の叫びだけが、取り残された静寂な室内に大きく響き渡った。
(PR)