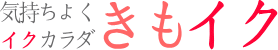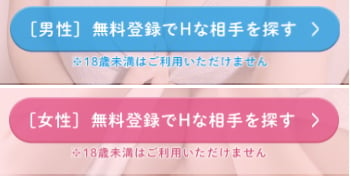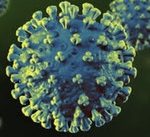慰めになりたい【きもイクラブ官能小説】

ワンナイトラバーズ
「オレに時間くれない?」
太賀の在り来たりで野蛮な誘い文句に、紫音は笑みを浮かべて応えた。
「私も同じ事考えてた」
間接照明も手伝い、彼女のその笑みは妖艶に見えた。
ラブホテルの部屋に入って靴を脱ぐと、太賀は紫音の背中を壁に張り付け、血色の良い肉感的な唇に自分のそれを押し付け、彼女の両頬を掌の窪みでがっちり固定する。
感触を堪能するのではなく、重ねる角度を何度も変え、発情期の獣のように、紫音の唇を貪った。
「んっ、はぁ…」
(いいなあ、何か)
唇同士の僅かな隙間から、部屋の湿った酸素を吸い込みながら、彼女はぼんやり考えた。
(初めてだ、こんな咬み付くようなキス)
恍惚とそう思いながら、また酸素を取り入れようと唇を少し開けた時だ。
その瞬間を見計らっていたように、太賀は紫音の咥内に難なく舌を滑り込ませた。
(…ベイリーズ)
彼女の舌を絡め取ると、さっき声をかけたバーで飲んでいたらしい、甘くてクリーミーなベイリーズの味が、彼の舌にねっとりと纏わり付く。
(…酒の好み、アイツと同じ)
忘れようと していた顔を浮かべてしまった太賀は、小さな苛立ちを覚えた。
舌を絡ませるだけでは飽き足らず、吸盤のように強く吸ったり、ラムの味が混ざった唾液を流し込んだりと、まるで八つ当たりでもするみたいに、彼は紫音の咥内を掻き回した。
舌を吸われる少しの痛みに顔を歪めたが、彼女が痛いと抵抗する事はなかった。
消えない影(…重ねてるんだ、私に彼女の事)
お互いの唾液が絡まる事で生じる、水溜まりを踏んでピチャピチャするような音を聞きつつも、紫音は太賀の行動の真意を何となく読み取った。
憂晴らしの為の今夜限りの相手、お互いにそう割り切っている。
それでも、せめてこの瞬間は太賀の慰めになりたい、と紫音は切実に願った。
太賀の八つ当たりは、もうキスだけに止まらなかった。
キスしたまま彼は紫音の頬から手を離すと、そのまま彼女の服に移動した。
紫音の黒いジャケットの釦を1つ外してバサリと床に落とすと、次は淡いピンク色のブラウスの釦を外し始めた。
早く触りたい
ブラウスの釦を外す太賀の落ち着きのない手付きがそう言っていた。
首元を隠す第1釦に始まり、腰の辺りまでの釦を外したところで、彼はやっと彼女の咥内を解放した。
目を潤ませてうっとした表情の紫音、釦を外したブラウスの隙間から、チラリと見えるミルク色のブラジャー。
これらの要素は太賀の本能を逆撫でし、男の部分に精を蓄えていく。
彼は紫音のブラウスを腕に引っ掛けたまま肩を剥き出しにし、ブラジャー越しに胸に触れた。
男らしい、大きな手にすっぽり収まった2つの膨らみは、マシュマロのように柔らかく弾力もあり、彼の手によりぐにゃぐにゃと自在に形を変える。
しかし、それだけではすぐに物足りなくなった太賀は、ホックを外す時間すらも惜しいのか、膨らみを被う硬めの生地をずり上げた。
2つの柔らかな膨らみは、支えを失うと一瞬だけプリンのようにフルンと揺れて、彼の前に姿を現した。
露出された色白の肌と、その頂点にある小豆色の乳頭とのコントラストが太賀はもちろん、紫音さえもより深い官能の世界へ引き込んだ。
「すごいエロい」
荒い呼気混じりに独り言のような、低いけど通る声で言うと、彼は胸に顔を近付け、小豆粒程の頂に突き出した舌先を這わせた。
そして、もう片方の胸は揉んだり、色付く先端を、気紛れにクリクリと指先や爪先で弄ぶ。
「ぁっ、…んっ、」
ピンと芯を持ち、クランベリーのように色めく乳頭の付け根や輪郭を、指先や舌で辿られると、紫音の唇からは、自らの意思に反して、高く、鼻から抜けるような嬌声が漏れる。
その声に、太賀の胸がチクリと痛んだ。
(忘れてすっきりしたいのに…でも、無理だ、)
本当に忘れたいなら、雰囲気が似ている紫音を今夜の相手に選ばない。
忘れたいのに、忘れられない。
相反する2つの感情が複雑に入り乱れて、太賀の頭は混沌としていた。
熱い肉塊を欲して
「後ろ向いて」
乳頭から舌を離すと、胸から顔を離さないまま、低い声で静かに言った。
真意を悟らせない彼の声音に、紫音は何も口にせず、太賀に背中を向け、壁に両手を着けてお尻を突き出す体勢になった。
眼前に突き出されたそれに、太賀は間髪容れず、両手で感触を確めようとするが、化学繊維の黒いスカートとその下の薄いパンティが、彼の触覚を鈍くする。
太賀は両手でスカートを裾から捲り上げ、紫音の腰に引っ掛けて阻みを1つ取り払うと、ブラジャーと同じ色のパンティが彼の目の前に曝された。
食べ頃の白桃のような、双臀を被うパンティはレース状で、細かく繊細な網目からバター色の肌が覗いていて、何とも淫猥だった。
太賀はレースの上から双丘に触れると同時に、もう片手を前に回して、紫音の女の部分に触れた。
そこは体温以上の温度を孕んでいて、パンティに小さな染みを作る程に、甘く淫らな汁を溢していて、彼の中指と人差し指をしっとり濡らした。
「はぁっ、」
羞恥を忘れて悦ぶ女淫を触れられ、同時に尻朶へ自分の物とは違う熱く硬い異物を宛がわれ、紫音は湿った吐息を漏らして、ピクリと体を震わせた。
(この硬くて熱いのが入るのか、)
欲を蓄えた太賀の淫茎に、無遠慮に突かれる感覚を想像した彼女は、更にパンティを濡らし、果ては太賀の指先をも濡らした。
(欲しい、その硬くて熱いので私の中を痛いくらいに突いて、)
紫音のそんな破廉恥な望みは、すぐに唇の外に溢れ落ちた。
「もう欲しいわ、お尻のそれ、」
彼女の蕩けた声に、太賀はニヤリと笑みを浮かべて言うと、紫音のエロティックな蜜で濡れた指先で肌触りの良い布を擦らし、淫乱な湿地帯を露にした。
痛みと悦楽の狭間で
「奇遇だね。オレも、もう入れたいと思ってた」
精を蓄え切り、先走りすら垂らす怒張で、物欲しげな紫音を挑発するように、彼女の尻をペチペチ叩いて、天然の潤滑油が滴る秘裂に尖端を宛がった。
「いあぁっ…!」
肉襞を掻き分け奥へ進もうとすると、湿りを帯びているが蕩け切っていなかったのか、女の悦びではなく焼けるような痛みが紫音を襲う。
悲痛な叫びが喉の奥から出てくると同時に、彼女の瞳は潤み、大粒の涙が不規則に零れる。
痛みを与えた罪悪感、或いは頭の中を占める人物に集中したいからか、紫音が声を上げた瞬間、太賀の男らしく逞しい手が彼女の口許を覆った。
「んんっ!」
掌で紫音の声を受け止めながらも、彼は進める腰を止めなかった。
痛みを感じながらも彼女は抵抗する事なく、捩じ込まれる太賀の熱情を受け入れようとする。
「んはぁっ、」
すると、痛みを緩和させるように、紫音の秘門は徐々に濡れそぼり、彼の形に合わせて緩んでいく。
そんな彼女の反応を待っていたと言わんばかりに、太賀は熱塊を更に奥へ一気に進めていく。
「んんんっ!」
1番質量がある部分まで一気に収まったが、紫音は挿入初め程の痛みを感じてはいなかった。
寧ろ、その中にも甘美な悦びを感じていた。
彼女は壁に付いた爪に力を入れて、迫る痛みと快楽に喘いでいた。
しかしそれは、紫音だけではなかった。
(締まりキツっ、)
太賀もまた、痛いくらいの彼女の締め付けに、快楽を感じながらも痛みを感じていた。
吸盤のように、隙間なく密着された彼は、酷く湿潤で狭い道が己の形に沿って、弛緩するのを待った。
「っ、はぁっ」
彼女の隘路が滑ってうねる感覚に、太賀は呼吸を乱しながらも、神経を研ぎ澄まして吐精感を紛らす。
彼のなけなしの気遣いに、紫音の体からは殆んど痛みが退き、同時に緊張も解かれ、太賀への収縮が甘くなった。
待ちに待った感触に、彼は収まり切れてない昂りを、一気に捩じ込んだ。
「ッ…!」
体を貫かれる感覚に、痛みが紫音を襲ったが、断りもなく始まった太賀の律動により、それはすぐに愉悦へ変化した。
彼の尖った鈴口が、辿り着いた淫路の果てを、一定のリズム、速度で刺激する。
「んっ、んっ」
律動的かつガツガツした突き上げに、紫音の肢体がエクスタシーに奮える。
エクスタシーと微かな艶羨
情事特有の艶声こそ太賀の掌が受け止めて聞こえないが、ブラジャーから溢れた2つの膨らみ、レースに被われた白桃を思わせる尻が、重力に従ってゆさゆさ揺れ動く様が、彼の視界にはこの上なく淫猥に映り、彼の理性を奪った。
「…何がいけなかった?」
腰の動きを止めないまま、太賀が独り言のように呟く。
「こんなに好きなのに、忘れられないのに、」
最奥を突き上げる力とは反対に、彼の言葉は消え入りそうに弱くて、紫音の胸を痛めた。
「不公平だろ…!」
訴えるような叫びに呼応して、太賀の突き上げが急に強さを増した。
「んんっ…!」
奥だけを突き上げる動きから、ギリギリまで抜いては挿入する、大胆な動きに変わった。
太賀の動きに合わせて、紫音の肢体も大きく揺れる。
「ふぅ、っん!」
自らの快楽を求めて、ひたすらに律動を繰り返していた時だ。
(もう、キツっ、)
突如迫ってきた大きな悦楽の波を感じ、これ以上堪えるのが無理だと悟った彼は、残った力を全て出し尽くすように、最後に彼女の最奥を貫いて、蓄えていた精を吐き出した。
太賀の生暖かい飛沫が、ねっとりと絡み付いて紫音の蜜路を満たす。
迸りを感じた彼女は、体を痙攣させた。
「はぁっ、」
深呼吸と同時に太賀の体から力が抜けていき、紫音の口元を覆っていた掌を離した。
「はあっ」
窮屈さから解放された彼女の唇からは、溜め息にも似た長い呼気が飛び出した。
(イケなかったな。それに、明日産婦人科行かないと)
不完全燃焼だったからか、余韻に浸る事なく現実的な事を考えている紫音とは反対に、理性を取り戻した太賀は酷い虚無感に襲われた。
「うぅっ、」
彼は彼女の腰を強く両手で抱き締め、剥き出しの背中に頭を乗せると、低い声で啜り泣き出した。
(幸せだろうな、こんなに愛されたら)
ぼんやりそう考えながら、紫音は子供のように泣きじゃくる太賀の涙が止まるまで待った。
(PR)