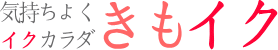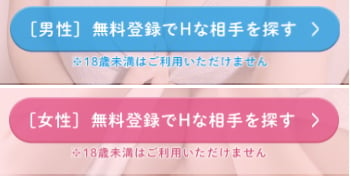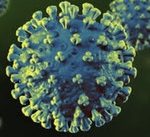吉原遊女の秘めたる色情

吉原遊女の秘めたる色情
欲を擽る肌
『年季が明けた日には1つだけ、何でも言う事聞くよ』
「夜明けまで、わっちの情男にするでありんす」
泣き虫だった禿と交わした約束は、15年後に高飛車な高級遊女と果たされる事となった。
自らの手で惜し気もなく曝された肌へ、吸い込まれるように乾いた唇を這わせた。外の空気に当たる時間が少ないからか、或いは若さ故か。唇や指の形が残らない千雪の肌は、しっとり潤っている。
首筋から手首、肩の線をなぞったまま、目線だけ彼女に向けた。
触れる度、ピクリと細い肢体が身動ぐが、視界の彼女は無表情を装っているが、いつ崩れても不思議はない危ういものだった。
きめ細かい肌に視線を戻して、椀と同じ形の豊かな膨らみに唇を下降させていく。肉が厚いそれは、一瞬だけオレを受け入れるが、他の部分と同じで緩やかに弾かれる。
柔らかさを記憶しながら肉の丘を登っていると、頂点の尖りに到達した。その部分は見た目通り、舌の中央に押し付けるだけでは形を崩せない位に、芯を持っていた。硬さと感触を味わいたいが、そこまでの時間も余裕もオレには残されていなかった。
名残惜しく思いながら、啄むように口付けて唾液を充分に纏わせてから、頂上をゆっくり離れた。
丘を下って次に辿り着いたのは腹部や脇腹。この2つの部分は他の部分より皮膚が薄く、鋭敏になっているのか、触れたとほぼ同時に千雪の体も少し大袈裟に跳ねる。しかし、彼女が見せる反応はそれだけではなかった。
「んっ、」
初めて聞く、控えめながらも濃い色を持ったくぐもった声。それに加え、肢体と同じ仕草を見せる左右の脚。
温度、うねり、濡れ具合、狭さ。見た事もない肉壁の細部や感触を想像しては気分を昂らせた時だ。
「…っ!」
彼女の素足が股間の隆起に宛がわれた。小さなそれは、ぐりぐりと押し付けるだけでなく、上から下へ棒の部分の輪郭をなぞったり、その下の丸い部分の形を確めてみたりと、器用な動きを見せる。
故意に核心を遠ざけるような焦れったい動きに、触れられた部分から熱を持って疼き出し、思わず四肢をぞくりと震わせた。
“早く入りたいでしょ?”
澄ました表情と足から、そんな千雪の挑発が伝わってくるようだった。それに乗るのは癪で、オレは押し付けられている足首を下から手で掴んで、動きを封じた。
「行儀悪い足」
仕返しして清々した気持ちを声に乗せてから、足首に唇を押し当てた。括れた部分から脛、太股と肌が柔らかくなっていく感覚を唇で味わいながら、核心部へと上っていく。
柔らかな内腿、脚の付け根まで上り詰めると、頬にふわりとした下生えが当たった。
(千雪と繋がれる)
その事実を目前にした瞬間、理性で鎮めていた昂りが急に暴れ出した。
魅惑の秘口
千雪と1つになる場所を見たくて、肉感的な太股をがばっと左右に目一杯開かせた。強制的に開かれた分厚い肉の先の結合部に顔を近付けてみる。
すると、仄かな熱気が鼻先や口許を刺激し、何とも言えない香りが鼻腔を擽った。
淫蕩な空気が常に漂う廓は、ヤりたい盛りのオレにとっては拷問のような場所。だから、気分と欲求と時間が合致した時には、コツや岡場所に行っては欲望を満たしていた。そうでないと、やってられない。
私娼の女郎は値が張らない分、質は高くなかった。媚を売る熱っぽい視線を向けては、鼻を塞ぎたくなる不快な匂いを漂わせる者も居た。
千雪から漂う香りは、そんな安い女郎達とは一線を画していた。数知れない男と閨を共にしたにも関わらず、病気や妊娠に嫌われた彼女の内側からは、甘美な香りすら放たれているように思えた。
甘い熱気に導かれるまま、得体の知れない生き物のように、小さく不規則な収縮を見せる肉孔を舌で撫でた。肉に触れた先端を、内から溢れ出る少しねばつく液体が汚した。味はよく解らないが、漂う香りと同じ、仄かに甘く感じた。微かなそれは後味として咥内に留まる。
咥内の甘みを濃くしたくて、口元と鼻先を密着させて奥へ侵入した。そして、中を潤す甘い汁を飲み干すような勢いで、ずるずると品のない音を立てながら無心に舌を動かした。
「ふっ、…んっ、」
千雪の下肢が小さく痙攣し、濡れ肉が僅かに舌を締め付ける。少し狭まった部分から抜け出て、下から彼女を眺めてみた。
頬は紅を引いたように赤く、瞳が水の膜の奥で不安定に揺れていた。完全崩壊してない人形のような澄まし顔が、千雪の最後の砦のように見えた。
何かを堪えるような複雑な表情が、加虐心にも似た感情を煽る。締まりを無くして水を滴らせる肉孔から、肉唇を少し尖らせた舌先で辿って頂上を目指した。小さな先端部が舌先に当たる。
唾液を充分に含ませた舌で、既に硬さを持つ豆粒程の突起物を満遍なく転がして触れる。
「はぁっ、っ…あっ!」
唇からは鋭く短い喘ぎ、指先まで目一杯伸ばしては宙を彷徨う脚、全体的に力が入って時折震える肢体。小さな豆粒1つで、千雪はあっさり快楽に服従した。例えそれが惰性的でも、理性を揺るがすには充分な反応だった。しかし、それだけでは物足りなさを感じるのも事実だった。
「千雪…どうして欲しい?」
丸めた舌先で弾いたり、唇や前歯で弱く甘咬みしたりと質量の増した突起への刺激を執拗で濃い物にして、言葉に代わって彼女の返事を急かした。
視界の端で宙に浮いたままの脚が不規則に痙攣する。
「ひっ、…あぁっ…!」
温度を込めた呼気を吹き掛けてから、小さな膨らみに強く吸い付く。
「いあぁぁっ…!」
母乳を飲む赤子のように呼吸が続く限り吸い続けていると、千雪は長く甲高い声を響かせ、一瞬だけ全身を強張らせると、宙に浮かせていた脚をくたりと畳に下ろした。
「はぁっ、はぁっ、」
「聞かせてよ、千雪」
悠長な声音で返事を催促すると、彼女は乱れた呼吸を繰り返しながらも応えた。
「寛蔵っ、」
頭上の声に導かれて顔を上げると両頬を掌で圧迫され、唇を押し付けられて呼吸を塞がれた。少々乱暴ながらも押し付けられたそれは、感触を確める時間も与えられずに離された。
「…私の中をっ、貴方で一杯に、してっ…!」
千雪の精一杯の懇願を聞いた途端、物足りなかった何かがじんわりと満たされていく感覚と、抑えていた何かが込み上げる感覚が1度に襲いかかる。もう欲望を抑える術がなかった。
葛藤と快楽
オレは脱力している彼女を立たせて肢体を反転させると、張見世のような細かい格子に手を着かせた。
「やっ、なにっ…!」
「これくらいの方が楽しいでしょ?」
驚くばかりの千雪に、からかうように言いながら、裾の中から股間のぶら下がりを解放した。取り出したそれは、彼女の痴態を目の当たりにしただけで、棒のように、しっかりと天井を向いて硬くなっていた。
突き出された下半身の白く双丘を目の当たりすると、オレの限界を代弁するように、肉棒が痙攣して頂点が行灯の光で妖しく煌めいていた。
左右の円い柔肉を掌で鷲掴んで掻き分け、拡がった割れ目から硬くなった肉の先端を侵入させた。入り込んだ先は、泥濘に足を突っ込んだようにぬるぬるで蕩けていて、快くオレを受け入れてくれた。
滑るように千雪の中に全てを収めたオレは、尻から手を離し、括れた腰を固定した。最奥を撫でるように、太股で臀部の柔らかさを感じながらゆっくりと腰を進める。
「あっ、はあっ!」
侵入が深まると、千雪の唇から抑えきれない艶声が漏れ出る。それは当然ながら、格子の隙間を縫って外にも漏れていく。
「そんな声出したら、外に聞こえるよ?」
言いながらも漏出を助長するように、後ろから上半身の左右の膨らみを潰すように掌で覆った。尻肉を弄んだように指先で掴んだりして形を変えていく。
時々、丘を形作る肉と違って芯を持つ先端も2つの指先で左右に捏ね回した。
「はぁ、あぁぁっ!」
裏茶屋が集まるこの一帯は1日通して人通りが少ないが皆無ではない。この瞬間、偶然通りかかったのが見世の人間で、千雪との情交を見られる可能性も充分ある。
廓内での男女関係は一級の御法度。知られた瞬間、制裁を受けて吉原を追放されるだろう。最悪の場合、千雪は身請けが流れるかも知れない。
しかし、そんな事態に陥る可能性はほぼない。
この辺りに来る奴らは秘密を持った連中ばかり。そんな奴等が、オレ達の逢瀬を公言できる勇気があると思えない。
「千雪っ、」
温かくしっとり濡れた肉壁を性器の全長で感じながら、最奥の少し硬い部分を撫で上げるように、そっと腰を打ち付ける。
「今、一緒に死んでって誘ったら、乗ってくれる?」
「はぁっ、…何と、物騒でありんすね」
格子の隙間を見詰めたまま、皮肉めいた笑みを含んだ声で言う千雪に言葉でなく、柔らかな臀部に小刻みに腰をぶつけて返事を催促した。
「一緒に、三途の川を渡るのも、粋でありんす…あぁっ!」
千雪が最後の言葉を紡いだとほぼ同時に、腰の打ち付けを速く強くした。
「嘘に、決まってるっしょ…その言葉だけで、満足っ、」
“いっそ心中でもすれば“
はっきり耳に届くようになった肌同士がぶつかる乾いた音、結合部から漏れる卑猥な水音が醸し出す淫靡な空気が、オレの胸中の隙に入り込んだ潜在的な欲求を消した。どうにも色欲には勝てないらしい。
「寛蔵っ、だめぇ…本当にっ、死んじゃうっ…!」
節々で長い嬌声を上げながら、甘い声で譫言のように言葉を紡ぐ。
「そのまま、逝かせてあげる…天国、」
腰の律動を変えないまま、オレは最奥を突き続けた。
悲鳴のような甲高く艶かしい声が部屋中に響く中、オレはそのまま生暖かい液体をぶちまけた。
「わっちの情男は終わり。早く何処か行きなんし」
行為を終えて身形を整えると、もう用済みと言わんばかりの態度で千雪が外を眺めたまま言う。不要な物を捨てるみたいな、鋭く突き放すような声音。彼女が吹かしている煙管の煙が、格子の隙間を抜けて夜空に消える。
不規則に動く千雪の背中に背を向けて、部屋を出ようとする。
「…吉原から出られて清々する」
吊り橋を渡っているような、不安定な震えた声を背中に受けながら襖を閉めた。
(PR)