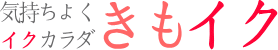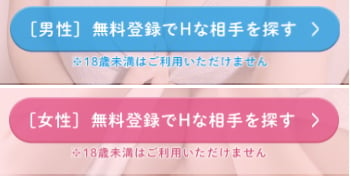もしも許されるのなら…1

「金輪際、私の前に現れないで」
今まで一緒に過ごした中で初めて聞く、強い口調で放たれた言葉に、由衣華は一瞬、言葉の意味を理解できなかった。
30歳を過ぎて初めての感覚だった。
友達から恋人になった日
はっきりとサバサバした男っぽい性格の、松崎静香。
そんな彼女は、夏目由衣華にとって憧れで、頼れるお姉さんみたいな存在だった。
しかし、高校1年でクラスメートとして出会って、友達という関係になり、一緒に過ごす時間が長くなるに連れ、それらの感情は彼女の中で、歪な形に姿を変えていた。
ある週末の学校終わり、いつものようにカフェチェーン店でお茶をしていると、由衣華は向かいに座る静香にこんな質問をした。
「どうすれば私はもっと、静香に近付けるの?」
そんな質問をしてきた由衣華は、まるで取り留めもない世間話でも振るような感じだった。
それに対し、静香は口に含んでいた生暖かいカフェオレをゴクリと飲み込み、目を丸くして、驚きを露わにしていた。
彼女の感情を乱したのは、空気を無視した唐突さだけではなかった。
(…由衣華も私と同じなんだ)
彼女も自分と同じで、独占欲にも似た感情を抱いているという事実を知ったからだ。
その事実は静香にとって、嬉しくもあったが、それは手放しではなかった。
嬉しさと、得体の知れないとっかかりの間で葛藤しながらも、彼女は由衣華の問いに答えた。
「だったら、私と恋愛してみる? そうしたら、今以上に私に近付けるんじゃないかな?」
静香の答えに、今度は由衣華が目を大きく見開いた。
(…同性の、しかも一番身近な友達に恋愛どうのなんて言われたら、そんな反応になるよね)
彼女がどんな反応をするか予想はしていたものの、一瞬だが実際に目の当たりにすると、静香は胸がチクリとした胸の痛みを感じた。
(…ダメだ、今の関係を崩したら)
そう自問自答して、質問の答えを取り消そうとした時だった。
「うん、静香と恋愛したい」
予想外にも、嬉々とした様子で由衣華は静香の言葉に乗ってきた。
―恋愛するってどういうことか知ってる?
―これからはお互いに友達じゃなく性の対象になるんだよ?
―私とキスできる? 裸になってセックスとかできる?
しかし、それらの突き詰めが静香の唇から放たれる事はなかった。
由衣華の嬉しそうな顔、そして何より彼女とより深い関係を築きたいという欲望。
「じゃあ、恋愛しよう?」
それらが、静香の唇から詰問ではなく、そんな答えを放った。
その瞬間から、彼女達の関係は友達から恋人へと名前を変えた。
関係を深める覚悟
端からは、ちょっと仲の良すぎる友達にしか見えないが、それが目に見えて変わる日を迎えていた。
「いくよ、由衣華」
「…うん…」
未知の領域に足を踏み入れようとする、恐怖から細くなる声で発せられた返事の後、静香は彼女の体を優しく寝かせて股がった。
そして、ぷっくりと赤く色づく唇を、自分のそれで塞いだ。
(由衣華の唇、柔らかくて気持ち悦い)
そう思いながら、人生で初めての感触を、静香は脳内や心に刻み付けるように味わう。
何れくらいか、そんな感じで酔しれていると、新たな欲望が彼女の中で顔を出した。
「舌、入れていいかな?」
重ねるだけじゃ物足りなくなり、由衣華の唇を解放すると、許可を求めるような声音で聞いた。
(…ゴメンね、気遣わせて)
「うん、入れて」
気を遣わなくていいから、という感情が少しでも伝わるように、由衣華は笑みを浮かべて、快く静香の欲をまた1つ受け入れた。
その言葉を聞いた静香は、舌を伸ばして再び唇を押し当てると、咥内を彷徨う由衣華の舌を、自分のそれで絡め取った。
ザラっとする舌先、滑らかな中央部や側面部、全体を潤す粘液の湿り。
絡めた舌全体を器用に動かしては、それら由衣華の舌が纏う感触を余す事無く堪能する。
「んっ…はぁっ」
制服とベッドのシーツが擦れる音に、お互いの唾液が混ざる水音、由衣華の乱れた呼吸音が加わり、静香の私室に淫靡な空気が漂い始めた。
(これから本当に、静香とセックスするんだ…)
部屋を漂うその空気は、由衣華の心身を同じ色に染めるだけでなく、一層そんな現実性をも持たせた。
(やっと由衣華と、深く繋がれる)
溢れ出す期待と欲望に心身の熱が昂ぶり始めた静香は、唇と舌を離した。
「直接、体に触っていい?」
「もう何も聞かなくてもっ、いいよっ…静香の好きなように、してっ?」
解放された咥内から酸素を取り入れながら、由衣華は息を切らしながらも答えた。
―由衣華に負担をかけさせないようにしないと
彼女が取った言動は、静香の内で渦巻き続ける底知れない本能のリミッターを、いとも簡単に崩壊させた。
「本当に、好きにするから」
最終警告のようなその言葉に、由衣華は何も返事をせず、ただ黙って静香を受け入れた。
迷いの無くなった静香の指先が、由衣華の首元を飾る紺のリボンを崩し、ブラウスのボタンを1つ2つと外していく。
鎖骨、胸元と徐々に彼女の肌があっという間に晒され、最終的に由衣華の上半身を隠すのは桜色のブラジャーだけとなった。
そんな霰もない姿のまま、静香は自身の指先と口元を由衣華の肌に近付けて、そのまま滑らせる。
「綺麗ね、由衣華の肌」
思春期特有の潤いや弾力、ハリや光沢のあるの素肌に、静香はただうっとりと酔いしれた。
(すごい、良い匂い)
鼻先を掠める肌から仄かに漂う、何とも表現できない甘美な香りに好奇心や欲を駆り立てられた彼女は、堪らずに舌を這わせた。
味を確かめるように、ゆっくりと色白の皮膚を舐め上げる。
「っ…」
ヒヤリと不意に肌を冷やされた感覚やくすぐったさに、由衣華はピクリピクリと不規則に肢体を震わせながら、短い呼気を吐いて再び呼吸を乱した。
色白の肌に舌を滑らせたまま、静香は片手で由衣華の脚へと移動させた。
そして、添えるように、由衣華の脚にそっと置かれたすらりとした5つの指先は、膝小僧からゆっくりとネイビーのプリーツスカートの裾を捲り上げ、内腿、最終的には脚の付け根にまで侵入を果たした。
(ああ…これで、本当にもう友達には戻れなくなる)
自身で勝手に引いた、友達と恋人の境界線を超える事へ一抹の寂しさや不安を覚えながらも、静香は布1枚隔てて、由衣華の陰処に指で触れた。
「ッ…!」
自分でも触った事のない場所を触られた羞恥と、鈍い火傷にも似た未知の火照りにか、まるで静電気でも通ったかのように、彼女の体がピクンと震えると共に、全身の筋肉が強張った。
「痛かった?」
静香のその問いに、由衣華は黙ったまま首を横に振った。
その反応を見た静香は、止めていた中指を動かした。
窪みから何かを掻き出すよう、入り口周辺の内壁に刺激を与えれば、擦り付けられている布に、由衣華の体温や分泌物が染み込んでいく。
汚物とはまた違うが、下半身からの排泄物に変わりはなく、触れるには自身のですら抵抗を感じる。
それが他人ともなれば、尚更感じずにはいられないが、静香は違っていた。
相手が由衣華なら抵抗が皆無どころか、湿りや体温が濃密になるに連れ、心身で悦びを感じていた。
心中に充満する独占欲や支配欲、触れてないのに、由衣華と同じ反応を見せる局部が、その証拠だった。
身動いだ拍子で、下生え越しに肌へ下着が擦れるだけでも、蕩けるような恍惚とした感覚が、静香の全身を駆け巡る。
そして、内壁の裏で分泌された高温の液体が、結合部を濡らすだけでは飽きたらず、1つ、また1つと布へシミを作り始めた。
一度、疼きを自覚した静香は、もう欲望を抑えられなかった。
悦びの共有
「ゴメンね、由衣華。じっくり、進めてあげられなくて」
語尾を言ったとほぼ同時に、静香は荒い手付きで、由衣華の肌を隠す衣類を取り去った。
色白の膨らみに、先端だけ赤茶に色付いた、碗型の乳房。
薄く肉の乗った括れたウエスト。
そして、生えて間もないであろう、毛並みの揃った薄く黒い繁みに覆われた生殖器。
同じ役割の器官が自身にもあるのに、眼下に広がる由衣華のそれらは、全くの別物に見えた。
自分にはない艶かしさに、静香は思わず息を飲んだ。
しかし、先に進みたいという欲求には勝てなかった。
剥き出しの肢体を観賞する事なく、静香は次に自身の衣類に手をかけ、1枚ずつベッドの下へ落としていく。
そして、やがて彼女も、由衣華と同じ姿になった。
(すごく綺麗で色っぽい)
由衣華もまた、眼前に晒された肢体から漂う妖美さに、息を飲む。
しかし、そんな感じで静香の裸を眺められたのも束の間。
自分にない艶かしさに、うっとりしていると、立てたままの両脚を左右に開脚させられた。
体を洗う時くらいにしか見ない部分が、静香の前に余す事なく晒される。
唯でさえ霰もない格好を、しかも愛しい恋人に見られているのに、これ以上に恥ずかしい部分を見られているが、腕や脚に力を入れて恥部を隠す事はしなかった。
(これでもっと、静香に近付ける)
羞恥以上に、そんな感情が由衣華の中で勝っていたからだ。
そんな由衣華の心身と、深く繋がる権利を得た静香は、暴いた下半身に股がった。
そして、自らの秘所を由衣華のそこへ押し付けた。
「はぁっ…っ、」
肌で味わう、今までに感じた事のない滑りと熱さに、静香は堪らずに熱っぽい息を吐いた。
呼吸を乱しながらも、彼女はより深い繋がりを求め、僅かにあった局部同士の隙間をも埋めて皮膚を密着させると、そのまま下腹部をゆるゆると上下に動かした。
「んっ、…はぁっ、」
触れて擦れ合っている部分が急速に熱を持ち、ジンジンと痺れる感覚をもたらす。
それは局部だけに留まらず、四肢やその末端と全身に及び、体温を上昇させた。
そんな肢体の変化を静香はもちろん、由衣華も感じていた。
しかし、彼女達の体に起きた変化はそれだけではなかった。
「静香っ、…熱いっ、溶けそうな位に、すごく熱いのっ…静香も、同じ…?」
生まれて初めて感じる性的な興奮に対する不安や、自分だけがこんなになっているという孤独感からか、由衣華は眉間に皺を寄せて切迫感や切なさなど複雑に感情が入り混じった表情で聞いた。
彼女のその言動は、静香に助けを求めているようにも見えた。
「同じっ、だよっ、」
静香のその答えを聞くと、由衣華はいつの間にか強張らせていた顔面の筋肉を弛緩させ、眉間の皺をゆっくりと消失させた。
「良かったっ…嬉しいっ、」
そう吐息交じりに答えた由衣華の声に負の感情はなく、言葉通り喜びに満ちていた。
自分と同じ感覚を共有してると解ったからか、彼女は安心したように笑みを浮かべた。
そんな彼女の言動を前にした静香もまた、純粋な喜びを感じていた。
腹の奥、或いはそこへ繋がる淫らに濡れた入り口に、張り巡らされた感覚神経の不規則な興奮のせいか、ズクンズクンと予測不能な疼きや、どうにも抑えられないむず痒さ。
そして、密接する部分から、熱い液体が生み出されてはトロリトロリと止めどなく零れ出す感覚。
それらの中にあるのは、最初に感じた火傷のような鈍い痛覚でも、不快感でも同性セックスをしている自分への引け目や不安でもなかった。
「好きだよ、静香っ、」
「私も好きだよっ、由衣華っ」
お互いにそんな睦言を交わし合うと、2人はどちらからともなく唇を重ね合わせた。
(やっと、由衣華と繋がれた)
未知の性的興奮を共有し心身で繋がれた喜び、このままお互いがドロドロに溶けて混ざり合えるのではないかというこの上なく蕩けた感覚だった。
静香と由衣華は、幸福且つ淫靡な一体感を心行くまで味わい続けた。
(PR)